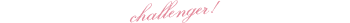プロフィール
酒田市出身
高校卒業と同時に青森県の津軽三味線の師匠のもとに弟子入り
1992年 酒田舞娘3期生「小鈴」としてデビュー
1999年 舞娘から芸者となる
2014年 日本舞踊藤間流師範となる
チャレンジのきっかけ
母親の影響で、5歳から民謡と10歳から津軽三味線を習っていた池田サユリさん。地元の高校を卒業すると、師匠のもとで津軽三味線を学ぶため、青森県で住み込みでの生活を始めた。三味線のお稽古はもちろん、師匠の家族の世話から家事まで、息つく暇もないほど慌ただしく過ぎる日々。結局、弟子入りをして半年ほどで体調を崩し、帰郷することとなった。
それから数年間はアルバイトをしながら過ごしていた池田さんは、知人からの紹介で、商工会議所で「舞娘」の募集をしていることを知る。誘われるままに面接を受けに行くと、その日のうちに稽古場へ。そのまま稽古が始まり、自然と舞娘への道を進んでいった。
「三味線や民謡は得意でしたが、踊りはほんの少しかじった程度でした。でも、自分の鬘(かつら)ができあがってきたその日に舞娘デビューをして、周りからは今までで最速だと言われました」
通常、踊りの稽古や立ち振る舞いなどを覚えてお座敷に上がれるようになるまでに必要な期間は、最低でも3カ月と言われている。しかし、池田さんは3週間ほどでお座敷に上がるようになったという。
チャレンジの道のり
平成4年に池田さんの舞娘生活が始まることになる。お座敷を務めながら、自分の支度はもちろん、ほかの舞娘達の着付けも池田さんが担うようになっていった。
「着付けを担当する人も、芸者のお姉さん達も、どんどん年齢が上がっています。そのため、着付けなどできることは手伝うようにしていました。時にはお姉さん達がお座敷に来ないということもあり、お座敷ではお客さんが待っているので、私が唄と三味線の『地方(じかた)』をして、舞娘を躍らせるようになっていきました」
それから7年が経ち、結婚を機に舞娘を引退したが、出産後には「芸者」として再びお座敷へ上がることとなる。
「舞娘を引退して、子どもも授かったので、芸者になることはまったく考えていませんでした。でも先輩のお姉さんや後輩の舞娘たちに頼られると、断ることはできませんでしたね。その頃は芸者としての収入が少なかったので、フリーで始めた司会業もやりながら、時には子どもをおんぶして2足のわらじでお座敷に上がっていました」



現在の活動内容
藤間流の名取を取り、2014年には『師範 藤間好百合』を取得た池田さん。現在は自ら芸者としてお座敷をこなす一方で、藤間流師範として舞娘達へ踊りの指導を行い、更に後輩の育成にも力を注ぎ始めている。
「踊りを本格的に始めてから師範を取得するまでは20年ほどかかりました。この業界はずっと前から後継者不足で、先輩芸者や師匠たちも年齢を重ねてきていたので、そろそろ私の代にバトンを渡してもらう準備を始めておかないといけないのかなと思っていました。そして司会業を辞めて、この道一つでやっていこうと決めた矢先、私の師匠が倒れてしまったんです。私がやらなければという使命感がありました」
池田さんは、かつて師匠の稽古場があった場所の向かい側、「舞娘茶屋 相馬樓」のすぐ近くに、踊りの稽古場「花柳界伝承舎 酒田 小鈴」を開いた。建物の外壁の色は「相馬樓」と同じ朱色だ。
踊りを教えるホールにはステージも設置されており、着付けをする部屋も備え付けられている。
「一見、華やかに見える業界ですが、芸事の道は本当に厳しい。なかなか後に続いてくれる若い世代がいないというのが現状です。そんな中、舞娘時代の後輩が、私のところで稽古をしたいというので、今、その後輩の面倒を見ています。事務所と稽古場が必要だったので、どこか場所でも借りて始めようかと思っていました。いろいろなご縁や周りからお力添えがあり、タイミング良く、稽古場を建てることができたんです」



今後の目標・メッセージ
春には、小さな子どもから高校生ぐらいまでの世代を対象に、日本舞踊、着物の着付けや礼儀作法なども身に着けられる教室を始める予定だ。
「ここは北前船交易で栄えた港町酒田。かつての繁栄を象徴する花街文化を継承していきたいと思いますし、舞妓や芸者になりたいと思う若い人がいたら支援もしていきたいと思います。今の私は、監督兼プレイヤーとして、舞妓たちの指導もしながら、お座敷にも出ています。でも将来は、若い世代の活躍を陰で支える監督へシフトしていきたいと考えています。そのためには、芸事の伝承をしっかりとできるように、三味線や長唄など、たくさん学習する必要もあります。師匠や先輩達からの宿題はまだまだたくさんありますね。」