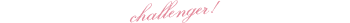プロフィール
1976年東京の下町に生まれる。
結婚後、夫の地元である大江町へ移住するが、その後夫の転勤で兵庫県へ。
ベビーマッサージ教室に通いながら、講師の資格を取得。
2013年にベビーマッサージ講師として、兵庫県で活動をスタートさせる。
2014年に大江町に戻り、以来地元を中心に教室を開催中。
また、乳幼児子育てサポート協会認定アドバイザーとして、講師の養成にも力を注いでいる。
チャレンジのきっかけ
東京生まれの東京育ちの鈴木さんは、16年前結婚を機に夫の実家がある大江町に移住した。「なんとかなる」という思いで新しい土地での暮らしを始めたものの、今までとは180度違う生活環境に戸惑うことも多く、孤立感を感じていた。その思いは、長女が生まれても変わることはなかった。
ずっと泣いている娘と話を聞いてくれない夫(今となると泣き続けている、話を聞いてくれないと思い込んでいたのではあるが)。そして自由のない生活に自分だけが我慢して、追い詰められていると感じ、育児を楽しむ余裕は全くなかった。
そんな時、たまたま参加したのが、産婦人科病院で開催されていたベビーマッサージ教室だった。娘と2人で参加し、そこにいた子育て中のママたちと同じような悩みを話し合い、分かち合った。この教室に参加したことが、子育て生活を楽しむきっかけとなった。
それから数年後、夫の転勤で兵庫県へと住まいを移したが、次女の誕生をきっかけに、久しぶりにベビーマッサージ教室に参加した。「触れ合うことで赤ちゃんにとっては“生きる力”が育まれ、お母さんにとってはより子どもを愛おしく思える効果がある」というベビーマッサージの大切さを改めて実感し、いずれ山形に戻ったら、ベビーマッサージで産後のお母さんたちの力になりたいと決意した。
チャレンジの道のり
次女の誕生から1年後、ベビーマッサージの資格を取得し、講師としての活動をスタートさせた。ちょうどその頃、もう一つの出会いがあった。現在、乳幼児子育てサポート協会の代表を務める行本充子(ゆくもとみつこ)さんだ。行本さんは、7人に1人のママが経験しているという「産後うつ」の問題に取り組み、うつの前段階にいるお母さんたちの気持ちに寄り添うための協会を立ち上げようとしていた。その思いに共感した鈴木さんは、協会設立後すぐに認定のインストラクターとなった。
2014年3月に大江町に戻り、子育てしながらその2か月後にはベビーマッサージ「arch(アーチ)」を設立した。ブログなどで告知しながら教室やワークショップを開催し、一人ひとりと信頼関係を築きながら、乳幼児子育てサポート協会認定アドバイザーとしての専門的な立場で産前産後のお母さんたちの応援を始める。
現在の活動内容
鈴木さんの軸となる活動は、ベビーマッサージ「arch(アーチ)」だ。山形市を中心にベビーマッサージ教室や父親教室などを開催している。これまで教室に参加してくれた親子は、延べ2,785組にのぼる。
ママたちに話を聴くと、仕事の忙しい夫には子育てのことを相談しにくく、何もかも自分ひとりで頑張らなきゃという気持ちになっている人が多かった。夫も父親になるのは初めてのことなので、妻にどんな言葉をかけたらいいのか、何から行動したらいいのかわからないはず。子育てを経験している先輩ママとして、気持ちのフォローをしていけたらと思った。
ベビーマッサージ教室に参加したママたちから、何気ない会話の中でお母さんたちの悩みを聴く。「ひとりじゃないから大丈夫」、「つまずいたり、育児に自信が持てないのはみんな一緒だよ」という鈴木さんが発する魔法の言葉に救われ、笑顔を取り戻すお母さんたちも多い。
子どもが生まれて幸せなのだが、毎日が楽しくないという方がいて、そんなことを思う自分がいけないんだと葛藤する人も少なくない。悩んでいる人は、「私は頑張っていない」と言う。自分の育児に没頭していると、自分の頑張りに気づけないし気づく余裕もきっかけもないのだ。ママはみんな頑張って子育てしている。話をよく聴き、それぞれの現状を理解しながら「大丈夫だよ。頑張っているね。」とママたち一人ひとりに伝えられたらと思っている。
ベビーマッサージ教室の他にもランチ会を開いたりしながら、子育て中のママたちの出会いの場を提供している。また、乳幼児の子育てをサポートするアドバイザーとして、東北地区で講師の養成にも力を注ぎ、これまで15人のインストラクターが誕生した。現在、県外のアドバイザー、インストラクターたちとオンラインミーティングを開催して情報交換を行うなど、県内外の枠を超えて協力し合いながら、お母さんたちの育児を応援している。




今後の目標・メッセージ
「今後の理想は、産婦人科や、行政が開催する母親・父親学級、両親学級との連携です。今のところ、県内でインストラクターがいるのは新庄・米沢と村山地域。今後はさらに県内外にインストラクターの仲間を増やし、一人でも多くのお母さんたちに寄り添っていきたいです。
産後だけでなく産前からいろいろな場でお母さんたちと信頼関係を築いていくことができれば、産後の孤独感や悩みにも深く対応でき、より安心して頼れる場所づくりにつなげていけると考えています。産後うつを未然に防ぐ一助となれるように、可能性のあることにはチャレンジしながら、お母さんを応援していく活動を続けていきたいです。」