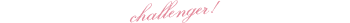プロフィール
2010年 都道府県、市区町村など自治体と全国規模の企業・団体等と共催で認知症サポーター
養成講座の講師役「キャラバン・メイト※」(全国キャラバン・メイト連絡協議会
主催)の資格を取得。
※キャラバン・メイトとは、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守
る応援者となる「認知症サポーター」を養成する「認知症サポーター養成講座」の講
師役を務める人のことを指す。
「キャラバン・メイト」になるためには、所定の「キャラバン・メイト養成研修」を受
講し、キャラバン・メイトとして登録する必要がある。
2016年 三川町で「にこにこメイト」を結成。
チャレンジのきっかけ
鶴岡市で生まれ育ち、高校卒業後は、プログラマー、薬剤助手、不動産関係の仕事などに就いてきたが、結婚を経て夫の地元の三川町へ移住。夫の母が脳梗塞を患い、介護をする中でその必要性に気づき、介護の仕事に興味を持つようになる。
バブルが弾けた時期に景気悪化のあおりを受けて、勤務先で退職を迫られたこともあり、その時にホームヘルパーの資格を取得。これまで知らなかった介護業界で働くことのきっかけとなった。
介護の仕事においては、姑の介護を行ってきたこともあり、利用者の気持ちや介護にあたる人の苦労がよくわかった。利用者や介護従事者の話を聞き、身内のように仲良くなり、利用する人が笑ってくれることにやりがいを感じながら、楽しく介護業に従事していた。
チャレンジの道のり
2005年に厚生労働省が「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」構想の一環である「認知症サポーター100万人キャラバン」をスタートさせた。これは、認知症の人とその家族の応援者である認知症サポーターを全国で養成し、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをやっていこうという取り組みだ。介護福祉士ということもあり、仕事に活かしつつ地域のためになればと思い、全国キャラバン・メイト連絡協議会が主催する「キャラバン・メイト」の資格を取得し、認知症予防や介護者へのサポート活動を始める。
三川町内でも数名のキャラバン・メイトがそれぞれ活動をしていたが、土田さんはキャラバン・メイトの仲間と共に新たに「にこにこメイト」という組織を結成。認知症に関する正しい理解を持った認知症サポーターを養成することを目的に、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることができる地域づくりを目指す。はじめは三川町の健康祭りを中心に、小学6年生とその保護者を対象として、寸劇を取り入れた笑いのある認知症サポーター講座を行った。

これまでの『認知症サポーター養成講座』は一方向に話すスタイルになりがちだった。にこにこメイトとしては、双方向でコミュニケーションがとれるように独自のスタイルでやっていこうと、2016年度からは参加者でグループを作り、お茶を楽しみながら話し合える講座をスタートさせた。メンバーは8人で、全員が福祉の仕事の経験者であり、メンバー同士の悩みなども共有しながら活動している。
介護をしている時、内に閉じこもらないことが大事だ。現在、介護福祉士として楽しく働いているが、家族の介護をしていた時は違っていた。頑張っても評価される訳でもない。また、家族だからこそ感情が入ってしまい、なかなか時間で割り切れるものでもなかった。にこにこメイトとして活動していくことで、同じように介護にあたる人同士で話をし、悩みや出来事にも笑い合えたりする時間が少しでもあれば、介護する側の気持ちも楽になると思っている。
現在の活動内容
現在は町から委託を受けて、高齢者が元気に楽しく暮らせる地域づくりを目指し、そのための様々な活動を行っている。
認知症を知ることを目的とした座談会「にこにこカフェ」を年3回開催し、ここでは認知症予防を目的として、症状や対処法を説明している。身内に認知症患者がいる人には、現場での対応について相談を受けることを目的とした「にこにこ介護者ほっとカフェ」を年2回開催し、悩みを聞いたり支援制度などを紹介したりしている。
カフェに関しては、認知症の方はもちろん、その家族に寄り添うために、できるだけ参加者に声を出してもらえるように気を付けている。「健康の秘訣」、「生きがい」、「高齢者の暮らしにあったらいいサービス」など、各テーブルに、にこにこメイトが進行役として入り、話を引き出しながら、和やかな雰囲気の中で話ができるようにグループの時間を設けている。


カフェの形式も、ホワイトボードを使った講義形式のものもあれば、みんなでグループに分かれてお茶を交えた座談会形式のものもある。また、認知症のテーマ以外にも、介護予防を話題にしたり、参加者に一番伝わりやすい方法で会を運営している。中でも参加者に好評なのが、寸劇を交えてのカフェだ。にこにこメイトのメンバーもみんな力が入り、ユーモアを交えて劇を演じることで参加者たちにも笑いが起こっている。


活動の幅は次第に広がり、地域の公民館や福祉センターなどの公共施設から、小学校などの教育機関、地域の商業施設などでも開催するようになっている。
こうした認知症の人の理解は、ただ部分的に行うものではなく、地域の見守り隊として、学校に通う子どもたちや、施設内のスタッフにも広めて、地域全体で理解していくことが重要だ。現在では、こうした活動や認知症へ関心を寄せる人も増えてきており、カフェへの参加者も延べ350人を越えるほどになった。


今後の目標・メッセージ
にこにこメイトの活動を通じて、地域の人が社会とつながることは、介護者にとっても、認知症を知らない人にとっても大切なこと。参加してくれた人たちの心が明るくなって欲しいと思って取り組んでいる。
今後は、カフェに足を運ぶのが難しい人のために、希望がある町内会へにこにこメイトが出向いていく「出前カフェ」なども行っていく予定だ。
「おかげさまでたくさんの人にカフェに参加頂いていますが、本当に必要としているのは、地域、家庭にとどまっている人。出前カフェにより、そうした人が足を運ぶきっかけになってくれたら、地域のコミュニティはもっと広がっていくと思います。また、新しく認知症サポーターになった人の活動の場を作り、地域の人が歩いて参加できる身近なカフェを開催できるようにしていきたいと考えています。」
高齢化が進む中で、土田さんたちの活動の1つ1つが、高齢者の輪を広げ、安全安心の場所づくりとなり、誰もが社会参加できるような仕組み作りの一助となっている。