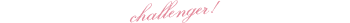プロフィール
1994年 夫の転勤で山形に移り住む。
同年 認定NPO法人 IVY(当時、JVC山形)で外国人支援を始める。
2015年 「山形てのひら支援ネット」を仲間たちと立ち上げ、「たまりばカフェ」を始める。
2016年 「山形てのひら支援ネット」で地域食堂「楽(ラク)」を始める。
福井県出身、山形市在住。
チャレンジのきっかけ
山形に移り住み、小さい子どもを育てながらできる仕事はないかと考えていた時、以前から学んでいた中国語が活かせるのではないかと、山形を拠点に外国人の支援活動を行なっている認定NPO法人 IVYを訪ねたことがボランティア活動のきっかけになった。
1994年当時、山形にはすでに結婚による海外からの移住者が多く住んでおり、IVYは日本語教室と通訳派遣という形で、その人たちの支援を行なっていた。2010年以降はその子どもたちが増えたため、山形市教育委員会の日本語支援員としても登録し、市内の小中学校で外国ルーツの子どもたちと関わるようになった。学校では日本語の支援が主だったが、いろいろな子どもと接するうちに、もう少し自由な関わりを持ちたいと思うようになった。折しも、全国で「子ども食堂」が立ち上がり始め、山形でもそういう場を作れないかと、それまでの支援活動で出会った仲間に相談したところ賛同が得られ、2016年7月に第1回目の食堂開催となった。
チャレンジの道のり
外国の人たちと関わる中で、言葉や文化の違いで誤解が生じ、家庭や職場で疎外感を味わいやすいことや、離婚してひとり親世帯になると子育ての不安も相まって、社会の中で一層深い孤立感を味わいやすい傾向にあることなどが見えてきた。一方、外国の人への支援活動は、関心を持つ人たちの範囲でしか広がらないということで、限界を感じることもあった。支援をしたくても資金調達が難しく、外国人となると「自分とは無関係だ」という人もいて、地域の理解を得るのも難しかった。
「これでは困窮する家庭のSOSを見逃してしまうのではないか」という不安を感じ、2015年に“食で育む子どもの居場所&大人の語り場”をコンセプトに「山形てのひら支援ネット」を発足させ、国籍等関係なく誰もが参加できる「たまりばカフェ」を、2016年には地域食堂「楽」の前身である子ども食堂「楽」の運営を始める。山形に住む外国ルーツの子どももさまざまだが、特に日本で生まれ育ち、日本語が母語の子どもの中には、支援が必要であるにも関わらず支援の網から漏れてしまうという子どももいる。資金調達、メニュー作り、食材の提供について、地域との関わりの中でどのようにネットワークを構築していくか。試行錯誤を繰り返しながら解決策を見いだしていった。
現在の活動内容
「山形てのひら支援ネット」としての主な活動は、地域食堂「楽」、20代の若者の居場所「プレイス」の学習支援を含む運営、コストコ配送やスタッフの研修会などで、会員、賛助会員あわせて約30人で活動している。地域食堂の活動は月2回。毎回60食のお弁当を用意し、初めて利用する場合は事前に電話で予約してもらい、利用経験者には毎回出欠の確認をする。コロナ禍前までは、会食形式で食堂を開いてきたが、現在はテイクアウトにシフトせざるを得なくなった。地域食堂に参加する会員は毎回7人前後で、高校生・大学生・地域ボランティアの協力も得ながら続けている。
また、2021年度は「やまがた女性のつながり緊急サポート事業」も受託している。提供してほしいものは何かを参加者に尋ねたとき、「日用品」という答えが返ってきたことは意外だった。県から生理用品配布支援の話があった時は、まずは配布をしてみて参加者の声を聞きたいと思い、事業に手を挙げた。コロナ禍になり、大学生の中にも孤立や貧困が広がりつつある状況も伺える。地域食堂は支援を必要とする人たちに近いところで活動していることを実感している。
いずれの活動も、さまざまな困難を抱えながら支援に辿りつけずにいる人や、社会的に排除されがちな人を対象に、国籍、性別、世代関係なく誰もが生きがいを持って暮らせる社会の実現を目指して行なっている。何もないように見えて、人に言えない生きづらさを抱えている人がたくさんいるが、一生懸命に生きていることに敬意を払いながら支援していきたい。「山形てのひら支援ネット」を居場所として必要とする人がいる限り続けていきたいが、そのためにはさまざまな世代の関わりが必須と考えている。



今後の目標・メッセージ
「不安や生きづらさを感じている方だけでなく、関心がある方もまずは地域食堂に来てください。私たちの活動にスタッフ、利用者という線引きはありません。みんなが参加者という意識で活動しています。 “青信号”だった人が、いつ黄信号、赤信号になるかわかりません。そんなみなさんの居場所として利用していただきたいです」。