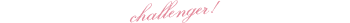プロフィール
平成16年 7月 マタニティ&ベビーケアQUEEN’S PRANAを起業
平成22年 三井病院「マタニティヨガ教室」「ベビーマッサージクラス」開講
NHKカルチャー教室「アーユルヴェーダクラス」開講
平成23年 藤島体育館「やさしいアーユルヴェーダとヨガ講座」
平成24年 チェリアdeカフェ「妊活ヨガ講座」
平成25年 「新緑の羽黒を訪ねヨガをする会」講師
エンジェルスキップ「こどもといっしょ、オーガニックなお茶べり会」講師
山形観光物産協会「温泉でデトックス&ヨガ&ほっこりランチ」講師
湯野浜温泉観光協会「YY朝元気プロジェクト」講師
チャレンジのきっかけ
3児の母として自らオーガニックな生活を実践し、経験を活かしながら、マタニティヨガやベビーマッサージを中心に産院等で妊産婦のケア、企業等でのヨガ指導、アーユルヴェーダやアロマテラピーの講師として活躍している。静岡県で生まれ、神奈川県で就職。独身の頃から、ヨガやアロマテラピー、整体、リフレクソロジーなどを習得。
結婚し、出産にもその経験を活かしたいと考え、自らバースプランを産院に提出し、長女を出産。女性の心と身体をサポートするQUEENS PRANA(クインズプラーナ)を主宰するきっかけとなっていく。
子育てと仕事の両立やバランスに葛藤、2人目妊娠の際に不安を抱いているなかで出会ったのがアーユルヴェーダの考え方で、自然の摂理を生活に取り入れていくというインドの伝承医学の講座を主催していた助産師さんとの出会いが活動のベースになっているという。
チャレンジの道のり
アロマやアーユルヴェーダを取り込みながら2人目を無事に出産した上野さんは、その助産院から産後の母子ケアを依頼されたことをきっかけに、平成16年7月に起業。自然分娩を提唱しているクリニックなど、産院、助産院でのマタニティヨガとベビーマッサージ講師、さらに都内のスポーツクラブ、スタジオ等でのヨガ、アロマテラピー講師などを務めた。
平成21年に夫の転勤に伴い鶴岡市に居を移してからは、三井病院(鶴岡市)でのマタニティヨガとベビーマッサージ講座、NHKカルチャー教室「アーユルヴェーダクラス」の講師を務めるなど、活躍の場を庄内へと広げている。
「マタニティヨガとベビーマッサージを担当しながら、お母さんたちが考えていること、悩んでいることを学び、必要なことを肌で感じて、実践できることを提案していきたいと思い起業しました。庄内に引っ越してからはママ友からの紹介などにより、仕事がどんどん広がっていきました」
現在の活動内容
「庄内は自然が豊か。自然の中でヨガをしていると、どんどん感覚が研ぎ澄まされます」と話す上野さん。
現在の活動内容は、平成25年に実施された主なものだけでも、チェリアdeカフェ「妊活ヨガ」、「新緑の羽黒を訪ねヨガをする会」、山形観光物産協会「温泉でデトックス&ヨガ&ほっこりランチ」、湯野浜温泉観光協会「YY朝元気プロジェクト」と幅広い。高校での保健講話や医療関係者の研修会講師、企業のPR誌やフリーペーパーへの執筆も行っている。


「山形観光物産協会さんのツアーは、湯野浜の温泉旅館とコラボしてヨガで気持ちよくなってもらうもの。これをきっかけに湯野浜観光協会さんのヨガと朝市を組み合わせたイベントに声をかけていただいたり、普段はなかなか接点のない方とお会いできて、そこからまた違うものが生まれ、喜んでもらえることがすごくうれしいですね。チェリアの妊活ヨガは2年目で、実際に妊娠、出産された方もいらっしゃいます。また、アトピーやアレルギーをもつ子どもの母らが活動されている会「オーガニックお茶べり会」では講師として現場の話しを聞いたりしながらも、私自身も楽しみながら参加しているので、また次につながるという、いい循環になっています」
このほか、自主企画として、自然分娩を扱ったドキュメンタリー映画「玄牝(げんぴん)」(河瀬直美監督)の上映記念ラジヨガ&トークセッションなどにも関わっている。



今後の目標・メッセージ
活動を始めてから平成26年7月で丸10年。これからも新しいことを学びながら活動を継続していきたいという。
「日々、勉強です。初心を忘れずに続けること。これまでの活動を支えてくれた方々、ご縁をいただいた方々に感謝しながら、一人の出産した女性、母親としても恥ずかしくない生き方をしながら、続けていきたいと思っています」
「子どもの頃から障がいをもつ方々をサポートするボランティア活動に参加してきて、学んだのは何かをしてあげるのではなく、ただ一緒に寄り添っていることの大切さです。私がやっている活動も参加者のきっかけづくり。そこから参加者の生活が変わっていったらうれしいなと思います。山形は働いている女性が多く、不妊に悩んでいる方、妊娠後に精神的に不安定になる方も少なくありません。マタニティコンサルタントとしてしっかりサポートしながら、相談の多い更年期女性へのサポート、企業の社員、スタッフへのサポートもやっていけたらと思っています」