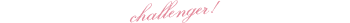プロフィール
平成20年 栄養士の仲間を募り食育活動を始める
平成21年 6月 栄養ケアもがみD-nyaの設立
平成24年 9月 大同生命厚生事業団「サラリーマン(ウーマン)ボランティア活動助成」に採用される
チャレンジのきっかけ
『栄養ケアもがみ D-nya(ダーニャ)』は、新庄・最上地区の管理栄養士・栄養士による食育活動をメインとしたグループ。新庄、最上地域内で管理栄養士として働いている三浦さんと柿崎さんが発起し、現在、14名(男性1名含む)のメンバーで活動している。
「同じ栄養士として交流をもつなかで、仕事以外にも、自分たちも縁を楽しみながら、栄養士として地域住民のために何か活動したいと意気投合。チラシをつくり、会員を募ったところ、同じ想いをもつ方々が集まってくれました」
「新庄・最上地区でも栄養士が活躍していることを地域の方に知っていただきたいという思いもありました。皆さん、とにかく職場以外でも栄養士として活動したい、地域貢献したいという思いの強い方々です。また、悩みを相談し合える栄養士同士の横のつながりができたことを喜んでくださる方もおられました」
チャレンジの道のり
最初の活動は、新庄駅・最上広域交流センター「ゆめりあ」でのおにぎりづくり教室。さらに、新庄市かもしかクラブ連合会主催のおたのしみ会に参加して、地域のお母さん方に栄養士としてサポートできるニーズをうかがい、現在の食育というテーマに辿り着いたという。
会を立ち上げてから1年後の平成21年6月には、名称を「栄養ケアもがみ D-nya(ダーニャ)」と決めて正式に団体を設立。山形県栄養士会からも地域住民のための食生活支援を行う活動として承認され、補助金を貰えるようになった。
「D-nya(ダーニャ)は、新庄弁で相手への共感を表す『んだにゃあ』に由来しています。Dietitian(栄養士)、natural(自然体)、young(若い)、accept(共感)、それぞれの頭文字を組み合わせて、いつまでも若々しく、人の話に自然体で耳を傾けて、共感できる栄養士を目指そうという意味合いを込めました」
「当初は活動資金がなく、あれこれ会員同士で知恵を絞り、地元の農協さんや業者さんに協力してもらったり、自宅にある食材や調理器具を持参して行いました。苦労した分、達成感があり、それはそれで楽しかったですね」
現在の活動内容
現在は、山形県栄養士会などからの補助金で行う年2回ほどの食育事業を中心に、自分たち独自の食育活動も実施している。平成24年度には大同生命厚生事業団「サラリーマン(ウーマン)ボランティア活動助成」を受けて、子ども向けの食育活動を実施した。かもしかクラブおたのしみ会への参加も、野菜の重量当てクイズなどと内容を工夫しながら継続している。
「真室川町北部小学校の親子行事では、地産地消をテーマにした親子料理教室を丸3年続けています。大人向けの食育活動としては、メタボ予防を目的に、保健指導的な講話とエクササイズを組み合わせ、さらに山形県栄養士会新庄地区会が考案したヘルシー御膳を提供して、半日メタボについて考えてもらう企画を実施しています。このほか、独身男女向けの婚活イベントとしてパティシエに教えてもらうスイーツづくり教室、介護ヘルパーさんたちとの調理実習などと様々です」
講話の依頼もあり、都合のつく会員が対応している。また、栄養士として常に新しい情報を得るための専門的な勉強会の開催も会の目的の一つ。
「例会や研修会は、ある病院に無料で会場を貸してもらったり、食事付の会として飲食店で開催するなど、できるだけお金がかからないように工夫しています。講師への謝礼なども全て自腹。会員同士で負担しています」


今後の目標・メッセージ
会員は20代から50代と年齢層が幅広く、活躍している職場も様々。このため、会議ではいろんな目線からの意見が出て、互いに刺激になり、勉強になるという。
「皆さん、個性のある方ばかり。設立から5年目を迎える26年春には改めて会員を募集して新しい風を入れ、ネットワークを広げながら活動していく予定です。入会の条件は、栄養士であること、栄養士という職業をこよなく愛してやまない人の2つです」
実施している食育事業についても、より多くの方々に参加してもらえるよう、広報の仕方、内容などに工夫していく考えだ。さらに栄養士目線での商品開発、在宅高齢者へのフォロー、ヘルシーレストランの運営といった構想ももちあがっているという。
「いろんな可能性を見据えながら、仲間と知恵を出し合い、自分たちも楽しみながら、地域に貢献し、盛り上げていきたいと思っています」
「新庄・最上地区の行政、施設には栄養士が未設置のところもまだかなりあります。そこに私たちが関わって、福祉と医療の連携をお手伝いしたり、健康に関することなら何でも気軽に相談していただけるような頼れる栄養士として活動し、住民の方々の健康管理のお手伝いができればいいのかなと思っています」