プロフィール
西川町月山志津温泉の旅館仙台屋に生まれる。
曽祖母の実家が月山和紙漉きを生業にしていたため、月山和紙が身近にあった。
現在は地元の月山和紙を素材にあかりを制作し、個展やワークショップを開催している。
また、あかりの演出や店舗照明制作なども手がけている。
1998年 東京の製菓専門校に進学
2000年 帰省中に実家である旅館仙台屋館内のあかりを独学で作り始める
2004年 あかり作りの講師・イベント出展を開始
2005年 家業を手伝うため東京からUターン
2013年9月 仙台・一番町「むかでや画廊」にて初個展を開催
2015年11月 仙台・青葉区「きものゝ老舗にしむら」にて個展を開催
2016年11月 イタリア・ミラノ「SAKEYA」にて展示・販売開始
2019年5月 台湾・台北にて展示・ワークショップを開催
2019年11月 東京・神楽坂「Ken’gallery」にて個展を開催
2021年7月 東京・ホテル雅叙園東京にて「和のあかり×百段階段」に初出展
2022年11月 金沢の百貨店・金沢エムザの美術サロンにて個展を開催
チャレンジのきっかけ
高校を卒業後、パティシエを目指して東京の製菓専門校に入った。卒業後は就職し、菓子店のオープニングスタッフとして働き始めたが、忙しい生活を送るうちに体調を崩してしまい、しばらくの間、実家に戻って休むことにした。
生まれ育った家は古くから月山志津温泉で温泉宿を営む旅館仙台屋で、休養中は家の周りにある枯れ枝や木の実、草花などを使って館内のディスプレイをしたりして過ごしていた。ある時、「玄関にあかりが一つあったら、お客様のおもてなしにいいな」と思った。子どもの頃から、祖父が身近にある自然のもので生活道具などを作っている姿を目にしていたので、自分であかりを作ってみようと思いたった。最初はブナの枝を拾い、あかりの形に組んで中に電球を入れた。しかしそのままでは眩しいので、和紙をつけたらどうかと考えた。それが和紙を手にしたきっかけだった。
曽祖母の実家が同じ西川町の岩根沢で月山和紙の紙漉きを生業にしていたので、家には昔の月山和紙の束があった。保育園の時、膨らませた風船に新聞紙や画用紙を貼ってお面を作ったことを思い出し、記憶を頼りに家にある和紙であかりを作ってみた。和紙を小さく手でちぎり、風船にノリで重ねて貼っていき、乾燥させて最後に風船の空気を抜いて取り出す。丸い形をしたあかりができあがり、和紙を通して柔らかく優しい光が広がった。あかりを作りながら自分自身も癒されていくようだった。
和紙のあかりを旅館に飾ると、西川町商工会の女性部の方から作り方を教えてほしいと声をかけられた。初めてあかり作りの講座をやってみると、とても楽しいと喜んでくれた。そこから口コミで広がり、次第にワークショップの依頼が増えていった。また旅館のお客様から、館内に飾っているあかりがほしいと言われるようになり、お譲りするようになった。
あかり作りに夢中になって、家にあった月山和紙をどんどん使っているうちに残りが少なくなってきたことに気がついた。色も生成りの1色だけだったので、いろいろな色の和紙も使ってみたくなり、他の和紙を取り寄せて使ってみたが、ゴワゴワしていてちぎった時のふわふわした手触りや毛羽立った感じが全く違った。作業もしにくく思うような形が作れない。いろいろと試してみたものの、月山和紙のような風合いのあかりができなかった。
「やはり気持ちよくちぎれて、きれいに貼れるのは月山和紙しかない」と、西川町大井沢で月山和紙を継承している三浦一之さんを訪ねた。地元や国産の楮(こうぞ)だけを使い手で漉く作業を実際に見せてもらい、これほど手間をかけて作るのかと驚いた。身近にありすぎてわからなかったが、月山和紙がどれほど貴重なものか、あらためてその価値を実感し「この月山和紙だけであかりを作ろう」と決めた。
PIC000133R.jpg)
チャレンジの道のり
2005年、家業を手伝うため東京からUターンした。シーズン中は旅館の仕事をし、オフシーズンの冬にあかりを作るようになった。全ての工程を手作りで、月山の豊かな自然をモチーフに風景を感じてもらえるようなあかりにしたいと、和紙の重ね方を変えてみたり、押し花にした葉を挟み込んだり、独学で技法を模索していった。あかりに使う月山和紙も、三浦さんにお願いしていろいろな色に染めてもらえるようになり、作品作りの幅も広がってますますあかり作りに熱中した。ワークショップの機会も多くなり、参加した人が誰でも気軽に体験できるように、作りやすさや教え方を工夫した。
こうして家業の傍らあかりを作る生活を続けていた時、旅館のテーブルなどを手がけている家具職人の方から、仙台の画廊で個展を開いてみないかと勧められた。ちょうど10年前のことだった。自分が個展をやるとは考えてもいなかったが、思い切ってやってみると県外からわざわざ足を運んでくれたり、通りがかりに画廊をのぞいてくれたり、たくさんの人が見に来てくれてとても評判が良かった。あかりを見てくれた人から「幸せな気持ちになりました」と言葉をかけられ、それが何よりうれしかった。それまでは地元の狭い世界で、いわば趣味で作っていたが、新しい世界が広がった。この個展をきっかけにあかり作りを仕事にするようになった。
月山和紙あかり作家としての仕事が中心になり、冬だけでなく他の季節にもあかりを作るようになると、新たな課題が生まれた。風船に和紙を貼って作るので、気温が一定でないときれいな形にするのが難しいのだ。冬場は暖房でノリが乾くので気にならなかったが、夏に窓を開けると風でノリが冷えてしぼんだり、寒暖差があると和紙がシワになったりと何度も失敗した。どうしたらいいか試行錯誤を続け、ようやく1年を通して形のきれいなあかりを作れるようになった。
作品の形もシンプルな丸いあかりからブーケのようなあかり、しずくやつぼみの形をしたものなど、バリエーションを増やしていった。例えばブライダルのブーケをイメージしたあかりは、月山和紙の素材感を伝えたいと思って作ったあかりだ。柔らかく薄くてもコシがあって破れにくい月山和紙の特長を生かして、ちぎった和紙を1枚1枚ひねって貼った。しずくの形は、風船の中に水を入れ、上から吊るして和紙を貼った。風船が伸びたり動いたりして形が変わるので、使ったことのなかった厚手の月山和紙を使い、穴をあけてみた。すると穴からキラキラと光がこぼれ、暗い場所に置くとプラネタリウムのような空間になった。
この和紙を貼ったらどう見えるか、この色とこの色を重ねて貼ったらどんな色になるか、光を通してみないとわからない。そこがあかり作りの難しさであり、わくわくするところでもあり、いつも一つ一つ悩みながら楽しみながらオリジナルの技法を考えている。
_H4A1611R-300x200.jpg)
D7K_3784-1R.jpg)
_H4A1648-2R.jpg)
PIC0004E3R.jpg)
_H4A1596R.jpg)
月山和紙の素材感を生かしブライダルをイメージした「ブーケ」(左)と月山の雪解け水を表現した
「しずく」シリーズ
現在の活動内容
約400年の歴史と伝統がある月山和紙を、もっと日常の中で身近に感じてほしいという思いであかりの制作とワークショップを続けている。和紙はどうしても和のイメージが強いが、そもそも楮という植物から生まれたもの。『植物のあかり』として、和と洋のどちらにも合い、月山の豊かな自然を感じてもらえる現代的なあかりの制作に取り組んでいる。また、楮が月山和紙になるまでにはいくつもの工程があり、職人の知恵や技、手間暇をかけた丁寧な手仕事から生まれることを伝えている。
ワークショップも和紙に触れてもらう大事な機会だ。今の時代は大人も子どもも和紙を使うことはなかなかないので、ワークショップでは実際に和紙をちぎってもらう。ふわふわしているのでちぎりにくいという人、ふわふわ感に癒されるという人と感想はさまざまだ。その感触を思い出して、和紙やあかりを生活の一部に取り入れてもらえたらと思っている。
あかりの創作では、予想もつかないオーダーをいただくことがある。去年、直径1メートルという大きなあかりのお話をいただき、いろいろ試して挑戦したが最終的に作ることができなかった。その後、直径80センチのあかりを作ってほしいという依頼があったが、その時は前回の経験を生かして作ることができた。難しいオーダーをいただくことでやり方や貼り方を試行錯誤し、そこから新しい技法が生まれ、あかりの世界が広がっていく。チャレンジする楽しさと同時に「うまくできるかな」というプレッシャーもあるが、お客様からそういう経験をさせてもらえるのは本当にありがたい。
20221210_153124R.jpg)
20221010220646_IMG_2309R.jpg)
D7K_001R.jpg)
今後の目標・メッセージ
今年も宮城や東京で個展の予定がある。個展ではいつも、周りの山にある木の枝や葉、木の実などを一緒に飾って、会場に月山の風景を作ってあかりを展示している。その空間の中に、これまで使っている和紙とは違う色味の紙で、印象の違うあかりを作って展示したいと新たな試みを始めた。
もう一つは、あかりと香り。和紙とアロマは植物同士でとても相性がいいので、自分で好きな香りのアロマを作り、和紙に垂らして、あかりと香りの両方を楽しめるようなものを考えているところだ。
月山和紙のあかりは、家に帰ってそのあかりを見た時にほっとして一日がリセットされるようなものでありたいと思っている。これからも大好きな月山の麓で、月山和紙で、そうしたあたたかくて優しいあかりを作っていきたい。
IMG_1472R.jpg)

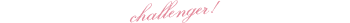

PIC000286R.jpg)
