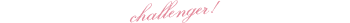プロフィール
宮城県白石市出身
大学卒業後、埼玉で2年間農業コーディネーターとして活動
山形へ移住し、大学や印刷会社に勤務
2017年 結婚 最上町赤倉温泉へ
地域おこし協力隊員
2022年 複合施設「une(うね)」をオープン
2023年~ 山形県最上町議会議員
チャレンジのきっかけ
実家が建築業を営んでいたこともあり、子どもの頃から、風景を作っているのは看板や建物を含めたデザインである、という視点で街並みを見ていた。日本家屋の造りや、素材を大切に生かすという父の考え方にも、自身の感性は少なからず影響されている。デザインの力で整った街並みは、住んでいる人の心も豊かにするはずという思いや、音楽が好きでミュージシャンのCDジャケットのデザインを描いてみたいなど、さまざまな意欲と未知のものに触れる期待感をもって東京の美術大学へ進んだ。
さまざまなことを学び、どのような仕事に就くかを考えたとき、デザインは素晴らしい仕事だが、その根本になる企画や編集もしっかりしていないと、デザインはうわべを覆うだけの装飾になってしまうことに気が付いた。デザインも好きだが考えることのほうがもっと好きだったため、編集・企画に関わる道に一歩を踏み出した。専門に学ぶ機会があったわけではないが、使う側の目線に立って、一般の人にもわかりやすいデザインを提供できると考えた。また、デザイナーの仲間、友人がいたことも心強かった。
チャレンジの道のり
大学卒業後は埼玉県で2年間、企画やマーケティング、食に関わる農業コーディネーターとして地域活性化のためのマーケティング調査や、農家と住民をつなげるワークショップを企画、実施した。地産地消という言葉が叫ばれ始めた頃で、関心は少しずつ高まっていたが、地元の野菜は同じ市内の飲食店にはまだ流通していなかった。そのため、まずは地元の野菜が地元の人に届く仕組みづくりとして、その土地で育った野菜を、高齢の方も多く住む団地に持って行き移動直売所を開くことから始めた。とても楽しく充実した日々を送り、農産物を作っている人が近くにいることが一番自然だと思うようになった。
2011年に東日本大震災が起こった。自分には何ができるかわからないが、人口が一人でも増え、東北にいて必要なときに動こうという思いから、東北に住もうと思った。山形に移住し、大学に3年、その後印刷会社に2年間勤務した。
山形という土地が好きでこのまま住み続けたいと考えていた頃、仕事で訪れた大蔵村で取材活動中に赤倉在住の男性と出会った。その後、イベントのボランティアスタッフとして一緒に活動し、結婚を機に赤倉へ移住。すぐに最上町地域おこし協力隊員になった。
最初は何をすべきかとまどいや孤独感があったが、自分で切り開こうと思い活動を始めると、はけごバッグを作る女性たちの「沢原はけごの会」との出会いがあり、ブランディングを手伝うなど一緒に活動を始めることになった。一つ一つ異なる素敵なデザインで、クオリティが高いはけごバッグを無料であげるのではなく、少しでも収入になるように販売できるようにした。行政主導の事業とは違い予算のない中、広報用のチラシを手作りして輪転機にかけるなど苦労も多かったが、山形エクセレントデザイン2021でエクセレントデザインプロジェクトデザイン賞を受賞し、大きな励みとなった。



さらに、地域を盛り上げようと、昭和40年代半ばまで続いていた最上町の伝統行事「むかさり行列」を、2018年5月に自らの結婚式でおこなった。新婦(当時は「花嫁」)を地域の人たちにお披露目をするために行列を作って練り歩くもので、調査や聞き取りなど準備を重ねた。地域の人たちが行列を止めて新婦に結婚の覚悟を問う「止め唄」と、応じる「返し唄」の練習も行い、多くの人が協力をしてくれた。こうしたことが新聞にも取り上げられたため、結婚式当日は取材陣やカメラマンのほか多くの人が参集した。昔を思い出して涙を流す人もいた。結婚式の会場は、その後複合施設「une(うね)」となる公民館を使用した。準備や掃除も自ら行い、式当日は新婦とウエディングプロデューサーの2役を担った。


その後産休に入り、復帰したがすぐコロナ禍となってしまった。地域おこし協力隊員としての任期の残り一年は、小さな広報という意味のフリーペーパー「小報もがみ」の発行を中心に活動した。月2回の全戸配布で、町にある資源、素材、身近な人を取り上げ、生活や生き方を共有する内容にした。外へ届けるのではなく、まずは町の人に身近な人のことをもっと知ってほしいという思いからだ。知人のデザイナーに文章に合わせた良いイラストを描いてもらうという協力も得られ、充実した活動となった。


現在の活動内容
「編集室」をいずれ立ち上げたいという思いがあったため、それに向けて素材集めや人と会うなど活動していた。あるとき廃校となった小学校に公民館機能が移転することが決まり「公民館は壊すことになるようだが、何か活用方法はないか」と地元の方から声をかけられた。公民館は、最上町の木材で作られていて、何よりも結婚式をあげた思い出の場所でもある。当初は小さい規模で編集室をやる予定だったので公民館の大きさに戸惑ったが、活用することに決め、改装費を自ら出して複合施設「une(うね)」を2022年4月にオープンした。
「赤倉編集室」は、“隣人の人生には、私たちの知らない世界があり、情報発信が何かと何かを結びつけるチカラとなる”ことを信じて、「une」に作った。「une」はその他にコワーキングスペース、こどもの遊び場、土産店、小さな食堂の機能を持っている。近くに室内の遊び場がなかったこともあり、こどもの遊び場の利用が一番多い。田舎暮らしの豊かさを再認識し、訪れた人の日々の暮らしが少しでも、さらに豊かになるような場所を目指している。年齢・性別問わず地元の人が交流できるように、定期的にマルシェや自然を体験できるワークショップなどを開催している。「une」は、知らない人同士が会話するきっかけになったり、子どもたちが自由な発想で遊ぶことができると、利用者に喜ばれている。
また、2023年には最上町議会議員となった。子育てをしながらの活動で多忙を極めるが、夫も同居の義母も力を貸してくれている。議員活動で「une」に居られない時には、母が代わりに入ることもある。




今後の目標・メッセージ
「豊さってなんだろう」と考えたとき、人や家族が食べる食事がおいしく安全であることが大切で、農業、食に興味を持った理由はそこにある。安心安全の食事ができ、守られている状態の最小単位が人、家族の幸せで、その集まりが地域になり、市町村になっていく。
「はけごの会」も、制作しながら会話も楽しむ場となり、そこに若い子育て中の人も加わると、年代は違っても共感し合い交流が生まれる。皆誰かと話をしたいという思いがある。産後、家族のサポートはあるけれど、同年代の話し相手がいなかったことで寂しく辛い時期もあった。この時に「思いつめなくても大丈夫だよ」と一言、身近にいる人や友達に言われたら少し救われたな、という思いがあり、この「une」は子育てする人たちが集まる場所になれればいいと考えている。
「ある方から、川に杭が出なければ流れが変わらない、出る杭は流れを変える役割を持っているという言葉を聞きました。何か自分もやってみよう、この施設を使って何かしたい、と思う人が出てきてくれることを願っています。人生を楽しむ、家とは違う場所の一つとして、施設の中でできることや、キッチンもあるので活用など相談してほしいです。無茶ぶりも歓迎です。企画も一緒に考えましょう」。