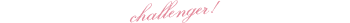プロフィール
平成 4年 「西荒屋フルーツ加工研究会」設立
平成10年 農家民宿「知憩軒(ちけいけん)」開業
平成15年 農家レストラン「知憩軒」開業
平成20年 農林漁家民宿おかあさん100選に選出
チャレンジのきっかけ
「昔の農家の女性は、働きづくめだったの。ちょっとコーヒーを飲みに行くことすら難しかった。でも心のどこかには『何かをしたい』という気持ちを誰もが持っている。家の仕事の合間に野良着でも気軽に来れるところがあれば、と思って『知憩軒』を作りました」。長南光さんは、自宅敷地内にある堆肥舎を改造し自由に寄り合える場として開放、近隣の女性たちがお茶や書道などをそれぞれに楽しみ、お互いの情報を交換しあった。「その頃も公民館はあったけれど、公民館の文化教室に集まる人はお茶も書道も上手な人ばかり。それにおしゃれしていかなきゃというイメージがあって、忙しい農家の女性たちは行きにくかったんですよね」。
軒の下で憩いながら、お互いが知識を得る場所”という意味で名付けられた「知憩軒」。長南さんは、今から10年ほど前に「知憩軒」を民宿として再スタートさせる。「その頃、家の仕事(農業)に加えて介護もしていたので、旅行に行くこともできませんでした。旅に出られないということは、それ以上情報が入ってこないということ。それならば、旅行者に家に来てもらえれば多くの人とふれ合えて、情報も入ってくるんじゃないか。毎日いる家を楽しい場所にしてしまおうと思ったんです」。近隣の女性たちの寄り合い場として使っていた離れ(元堆肥舎)にプレハブの建物を付け加え居住感を向上させただけ。改築には必要以上にお金をかけず、昔ながらの農家の風情を残した民宿が完成した。
チャレンジの道のり
「例えば稲作は、耕うん機や田植え機といった機械はその時期だけ稼働して、あとはお休み。田んぼも冬は稼働していません。それと同じように、民宿にお客さんが来ない日は農閑期、お客さんがいる日は稼働日って考えています。そうすれば、宿泊客がいないからといって焦ったり、あわてて宣伝したりすることもないですから」。農業的な発想から、あくまで自然体で民宿を運営する長南さん。しかしそこには、長南さんの農業に対する熱い思いがあった。
「茶碗1杯のお米が、いくらか知っていますか」。長南さんは、農業の現状を訴える。肥料の値上げ、減反政策、生産効率を上げるためには高額な農機具も不可欠だ。田んぼに引く水すら水利権としてお金で買う。天気に左右され不作の年もある。農業人の誇りとして有機・無農薬農法にこだわりたくても、家族を養うためには生産量を上げなければならず、不本意ながら農薬を使わざるを得ない。そして稲作農家の手元に残るのは、お茶碗1杯のお米を育ててわずか10円程という現実…。私たちが知らないところで、規模の小さい農家ほど悲鳴をあげている。「日本人は昔からお米を食べて精神をたもってきました。日本を支えているのはお米。だから日本のお米を守らなくちゃいけない、農家を守らなきゃいけないと思うんです」。
長南さんは、知憩軒を民宿として広く一般に開放した。「ここに来て、野をわたる風を感じ土に触れ、五感で自然の営みを感じてもらいたい。農村の暮らしそのものを見てもらいたい。そうして農業について少しでも理解してもらいたいんです」。 元は近隣の女性たちの“知”の場であった知憩軒は、今では農業を知らない日本人が農業を知るための場所になっている。


現在の活動内容
自身を「農家の応援団」という長南さん。「これまでの農家は作るばかりで、売ることに関してはまったくの素人だったわけです。せっかく汗水流して作った作物でも、形が悪いというだけではじかれ捨てられてしまう。だったらそれを加工して自分たちで売ればいい。そこでこの近隣の農家とともに『西荒屋フルーツ加工研究会』を立ち上げました。収穫期と収穫期の合間にその加工品を売れば、無駄がなくなるどころか収入の足しにもなりますから」。
平成20年長南さんは、農林水産省と国土交通省が連携して実施した「農林漁家民宿おかあさん100選」に選ばれた。「西荒屋フルーツ加工研究会」を立ち上げたように、自分だけが潤うのではなく、地域全体が活性し潤うようさまざまな活動に取り組む姿が評価された。 「いまこうして暮らしていられるのも、これまでいろいろな方から多くのことを教わったから。これからは私がお返しをする番だと思うんです。人と人とが出会う場面で出来る限りの時間を使いながら、次の世代の人たちにも守りたいものはしっかりと伝えていきたいですね」。