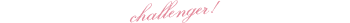プロフィール
昭和43年山形市生まれ。地元高校を卒業後、民間企業に勤務。
20歳より、山形こけし工人の父・梅木修一氏に師事し、こけしの描彩を始める。
2012年12月 山形こけしの継承を決意し、長年勤めたカーディーラーを退職。
東北・全国で開かれるこけし祭りにて、毎年数多くの賞を受賞している。
チャレンジのきっかけ
直美さんの父親は、山形こけし工人として名高い、梅木修一氏。幼い頃からその姿を見ていたが、直美さん自身は父の後を継ぎ、こけし工人になろうという考えは全くなかったという。
しかし高校を卒業し社会人となったある日、修一氏のファンから「娘さんの作品をぜひ手にしたい。」と切望され、悩んだ末についに筆をとることになった。
チャレンジの道のり
あらためてこけしの歴史を紐解くと、こけしは東北地方独特の工芸品で、江戸時代に農民が農閑期を利用し、子どもの遊び道具として作ったことがはじまりとも言われている。
その後、温泉場のおみやげとして発展し、現在11系統がある。山形こけしはそのうちの1つの蔵王高湯系で、蔵王温泉を中心に発達した。大きな頭に、三日月型の目。しっかりとした太い胴が特徴だ。胴模様には菊や桜などが鮮やかな色彩で描かれている。基本色の赤は、魔除けの色。医学が発達していない時代、子ども達の健やかな成長を願っていた背景がうかがえる。
「初めての作品を製作した後、そのことが口コミで広がり、次々と依頼が入るようになりました。そして、今回だけ、今回だけと言っているうちに数を重ね、今日に至ります。もともと美術が得意だったわけでもないですし、父も私が会社を辞めることに反対だったので、後を継ぐつもりはありませんでした。しかし、作品作りを重ねるうちに、高齢となった父からもっと多くのことを学びたいという気持ちが強くなり、思い切ってこけし工人に専念する道を選びました。」
現在の活動内容
2013年からこけし工人として新たな一歩を踏み出した直美さん。
これを機に、これまで行っていた絵付けに加え、こけしの土台を作る『木地修業』も始めている。美しい丸みを作りだす技は、一朝一夕に習得できるものではなく、修一氏からの指導を受けながら『習うより慣れろ』の精神で日々鍛錬を積んでいる。
作品は県内のみならず、全国にも発信。横浜や大阪など(主に高島屋)で開かれる山形の物産展や大東北展、全国職人展、そして東北各地で開かれるこけしまつりなどにも積極的に赴き、実演や作品展示などを通して魅力を伝えている。


今後の目標・メッセージ
最近では、こけし作りの技術を応用し、オリジナルのミニこけしや雛人形、だるまなども製作し、全国から注文が寄せられている。
また月山和紙や山形桐箱の職人とのコラボレーションを通して、新たな作品作りに挑戦している。こうした創作活動は『伝統を壊す』ことではなく、『伝統を守る』ことにつながる、と直美さんは考えている。
「伝統こけしの世界にいきなり入ることは難しいと思います。しかし創作・アレンジをした作品だと、かわいらしい雑貨を手にするような感覚で気軽に楽しんでいただけるのではないでしょうか。そうしたきっかけで、徐々にこけしについて学びを深めていくと、最終的に求めるのは『本物』。伝統こけしに辿り着くのではないかと考えています。最近は伝統こけしに魅了された若い女性の愛好家が、関東や関西を中心に増えています。伝統を離れて作品を作ることは、結果的に伝統を守ることにつながると信じています。」
「最近ファンの方から、『こけしの顔が変わったね。こけし工人に専念したことで、その覚悟が筆から伝わっているのでは。』と言われました。見た目は同じものを描いているはずなのに、不思議ですよね。まだ歩き始めたばかりですが、これからも父の教えを少しでも多く吸収し、山形こけしの伝統を守っていきたいと思います。」