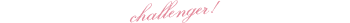プロフィール
1985年 新庄亀綾織伝承協会発足。亀綾織についての学習運動を開始。
1986年 亀綾織の基本といわれる「紗綾形」の復元に成功。
2001年 新庄駅前通りに体験工房「機織り長屋」をオープン。
チャレンジのきっかけ
新庄市に伝わる亀綾織(かめあやおり)は、新庄藩9代藩主正胤(まさつぐ)が文政13(1830)年に技術者を招き、藩の特産品として奨励したことから始まった絹織物。通常の織物によく見られる技法は平織りで、経(たて)糸1本と緯(よこ)糸1本を交互に交差させて織るため、糸の組織が縦と横で構成されるが、亀綾織は、経糸と緯糸を交差させる際、斜めになるようにする「斜文織」という技法を取り入れていて、高度な織り技術を要する。さらに、とても細い絹糸を使うため、きめ細やかな作業が必要で、10cm織り上げるのに名人でも丸一日かかかってしまうほど手間がかかる織物と言われている。
戦争や不況など時代の波に揉まれる中で、明治末期に生産が途絶え“幻の織物”と呼ばれた時期もあったが、昭和56(1981)年、亀綾織が国の「最上モデル定住圏における地域特産品の開発調査」に指定されたことにより、山形県が調査部会を設立。その翌年に県工業技術センター置賜試験場で9種類の地紋復元に成功したことを契機に、昭和60(1985)年「新庄亀綾織伝承協会」を発足。置賜試験場の専門員を講師に招き、亀綾織についての学習運動を開始した。


チャレンジの道のり
「新庄亀綾織伝承協会が発足した当時は何十人も会員がいて、20種類の地紋が復元されるなど、活発な活動が行われていたようです。その後高齢化などで会員が減少し、途中1名になった時期もありましたが、その後なんとか持ち直し、現在は7名の会員が所属しています。そのうち織り手は4名です。」
こう話すのは、会長の阿部友香さん。まだ30代という若い担い手だ。阿部さんが協会に入会したきっかけは、県の緊急雇用の求人を受けたもので、当初は期間限定の契約だった。阿部さんが協会に入りまずはじめたのは、復元された20種類の地紋の織り方を覚えることと、大型の機織り機の仕組みを覚えること。足の踏み方や糸のかけ方、はたき方の強さなど力加減がとても難しく、前かがみで長時間作業をするので、背中などが痛くなっていく。また、足と手を絶え間なく動かし続けるので、手足がパンパンに張るのに耐えて努力を続けた。その後、正規の職員として働き始め、会長に就任したのは4年前。発足当時からの会長が高齢のため引退することになったことがきっかけだった。
「私は地元に住んでいたのにも関わらず、亀綾織のことを全く知りませんでした。周囲にも知っている人は少なく、ご高齢のおばあさんがかろうじて知っているという程度の認知度でした。まったくの初心者の状態でスタートし、1年目は、織り方があっているのか、間違っているのかすらわからない状況。5~6年経ってやっと、徐々に仕組みがわかるという感覚になっていきました。亀綾織は図案が残っているわけでもなく、あってもメモ書き程度のものや、名前のみで図案がわからないということが多いんです。“~菱”とつけば、なんとなく菱形の模様かなという推測はできたりするのですが、資料が乏しい中での復元は、容易ではないというのが正直なところです。」



現在の活動内容




今後の目標・メッセージ
会では、全50種類以上あるといわれる亀綾織の地紋で、まだ復元されていないものを掘り起こそうと、1年ほど前から動きはじめている。また、織物を生業とする他地域の職人とのつながりをもちたいと、米沢織の職人と交流を持ち、織り方や、機の仕組み、メンテナンスの仕方などを学んでいる。
「現時点で、亀綾織の織り手になろうという人材は少ない状況です。その分、自分が伝統を継承する一翼を担っているのだ、という責任を感じています。今は小物を作るための布しか織っていませんが、近い将来、亀綾織の本来の姿である、“着物のための一反”を織り上げてみたいと考えています。ただ、一反織り上げるには数ヶ月を要します。長丁場を乗り越え完成させることができるよう、集中力と技術力をさらに磨いていきたいです。」(会長 阿部友香さん)
「若い世代の阿部さんが会長になってくれている今、この勢いで織り手を育てていきたいですね。ここでまた途絶えたら、本当に幻になってしまう。それはもったいないですから。新庄といえば新庄まつり!というのと同じように、亀綾織の知名度をあげていきたいですね。」(副会長 中川礼子さん)