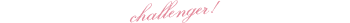プロフィール
1973年 寒河江市生まれ
東京農工大学農学部卒業
東京にてシステムエンジニアとして勤務
2016年 和田酒造合資会社入社
2017年 製造責任者となる
チャレンジのきっかけ
大学を卒業後、IT関係のシステムエンジニアとして、20年近く東京で暮らしてきた安孫子明子さん。2016年に山形へUターンしたのは、40代になったばかりの頃だった。
「30歳を過ぎた頃から、東京で暮らす中で『何らかの形で山形との関わりを持ちたい』と思うようになりました。東京で行われる物産展などで、山形芋煮のアルバイトをしたり、『山形みらいラボ』主催のワークショップに参加したりして『やっぱり山形はいいな』という気持ちが大きくなっていきました」
40歳という節目を迎え、実家の両親のことも気がかりだったため、いよいよ本格的にUターンを意識し始めた安孫子さん。高校・大学が同じだった友人の和田弥寿子さん(写真左)に転職の相談をしたところ、「それなら、和田酒造で醸造に関わってみる気はない?」と誘いを受けた。
和田酒造は、和田弥寿子さんが役員を務める、200年以上の歴史を誇る老舗の酒蔵だった。
チャレンジの道のり
以前から正月に帰省する度に、和田酒造で行われる「正月初しぼり」の出荷の手伝いをしていたことや、和田酒造の情報が発信されるSNSを常に見ていたことから、和田酒造はとても近い存在だったという安孫子さん。しかし、酒造りの知識はほとんどゼロ。50年間、杜氏を務める大ベテランの庄司長太さん(80)から、米や水の扱い方の基礎を学んだ。
「最初は、女性も杜氏ができるのかと不安でしたが、80歳という高齢の庄司さんもしているので、『自分にもできるはず』と思うようにして不安を払拭していました。以前から和田酒造の皆さんと顔馴染みだったので、すんなりと受け入れてもらえたように思います。もともと和田家は穏やかな方ばかりなので、働きやすい環境ですね。東京でのギスギスした生活とは比べ物になりません。ただ、蔵の中は寒いことが多いので、はじめのうちはよく風邪をひいていました」
酒造りが本格化する冬には、杜氏の庄司さんの他にも5人ほど造り手が来る。安孫子さんは、ベテランの先輩たちから短い期間の中で多くを学んでいった。
現在の活動内容
1年を通して酒造りを教えてくれた杜氏の庄司さんが引退を決め、安孫子さんにバトンが引き継がれたのは2017年5月。その半年後の冬には、独り立ちをして初めての酒造りが始まった。
安孫子さんが主に担当するのは、分析の仕事。毎朝、発酵中のタンクから分析用の“もろみ”を取り、アルコール度や日本酒度などを確認する。そのデータを杜氏と共有し、アルコール濃度の調整や絞る時期を見極めている。
酒造りのオフシーズンには、ITのシステムエンジニアをしていた経験を活かし、ホームページの管理を行うほか、東京や大阪、仙台などに赴いて、試飲販売などの販売促進活動をしている。
「冬だけでなく、夏や秋も季節限定のお酒造りがあるので、常に忙しく動いています。もともと同じことを繰り返す仕事は向いていない性分なので、変化があるこの仕事は、楽しいですね」



今後の目標・メッセージ
「この冬、独り立ちをしたばかりなので、酒造りについてわからないことだらけ、というのが現状です。これからも先輩方から教えていただきながら、酵母やきき酒の用語など、酒造りの基礎をより多く身につけたいと思います。また、今は昔ながらの帳簿を使用しているので、データ管理の効率化を少しずつ進めていけたらいいなと思っています。それから、弥寿子さんが手がけている女性向けの企画やイベントにも協力していきたいですね。小さい蔵だからこそできる企画に挑戦していきたいと考えています。せっかく地元に帰ってきたので、異業種交流や趣味などを通して多くの仲間を増やし、これからの酒造り、地域づくりに活かしていけたら嬉しいですね」
近年、海外でも人気が高まっている日本酒。地元河北町ではイタリア野菜の栽培が盛んなことから、ワインの醸造法を取り入れ、ワインを意識したパッケージの日本酒を共同開発し、話題になっている。和田酒造にもこの冬、イタリアからソムリエが来て酒づくりを学んでいった。新しい風が吹く中、安孫子さんの挑戦は続く。