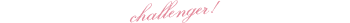プロフィール
1998年 「リース工房すぐりの実」を自宅にオープン
2001年 自宅を改装し、教室名を「カーラント花工房」と改称
2002年 湯の浜温泉内に「庄内クラフトステーション」を開設
2004年 「庄内クラフトステーション」にてプレクラフトフェアを開催
2005年 「庄内クラフトフェアin松ヶ岡」を開催(以降10年間開催)
2006年 松ヶ岡開墾場に「くらふと松ヶ岡こぅでらいね」をオープン
チャレンジのきっかけ
鶴岡市で15年専業主婦をしていたという石堂佳美さんが再就職を考えたのは、子育てがひと段落した40歳の時。就職の面接に行く予定だった日の朝に、友人から電話で「フラワーデザインを仕事にしなよ」と言われたことが、石堂さんの生き方を大きく変えた。
これまで、趣味として楽しんでいたフラワーデザイン。石堂さんは、友人のことばに背中を押される形で再就職ではなくフリーランスの道に進むことを選び、自宅でフラワーデザイン教室をスタートした。まだクラフト制作を仕事にする人が少なかった時代、「そんなものが仕事になるのか」と言われることもあったという。
ある時、自宅の玄関に飾っていた作品が新聞社の人の目にとまり、新聞の記事として紹介された。すると、「作品を展示してほしい」という依頼が来るようになり、個展を開催するまでに。徐々に教室が軌道に乗ってきたことを実感した石堂さんは、「リース工房すぐりの実」と教室に名称をつけて、本格的にフラワーデザインの指導を始めた。


石堂さんのフラワーデザイン作品
チャレンジの道のり
ある日、作品を見た人から「あなた、これ我流でしょう」と言われた。仕事としてするには、まずはその道に師事しなければならない、と気付かされたことばだった。石堂さんは、東京から有名な指導者が定期的に来県していることを知ると、その門を叩いた。以来、15年にわたり指導を受けた。
「今は簡単にクラフト作家になれる時代ですが、私が学んだのは『世界のトップを見なさい』ということと、『その歴史を知りなさい』ということ。トップを知れば、自分が今どの位置で、これからどう成長していけばいいかがわかります。しっかり基礎から学んだことは、その後の作品づくりに大きく役立ちました」
その後、自宅でおこなう教室のほかに、友人の誘いを受けて湯の浜温泉の一角でも「庄内クラフトステーション」の活動を始め、クラフト作家同士のネットワークを築いていった。試験的に開催した「プレクラフトフェア」は予想を上回る1000人の来場者を集め、大きな手ごたえを感じたという。
「全国のクラフト作家が集う、クラフトフェアを開催したい」というクラフト作家たちの機運が高まり、石堂さんも会場探しに奔走した。何度も断られる中、快く承諾してくれたのが、松ヶ岡開墾場だった。
全国規模のクラフトフェアは、山形はもちろん、近県では初めての開催だった。石堂さん自身、クラフトフェアを見たことがなかったため、すべて手探りでの企画だったという。
2005年4月、松ヶ岡開墾場で毎年開催していた「桜まつり」とともに「庄内クラフトフェアin松ヶ岡」を2日間実施すると、ここでも予想をはるかに上回り、5000人ほどの人が松ヶ岡に訪れた。
「開催のノウハウなど全くないまま企画したので、すべてが手探りでした。作家さんの泊まる所や食事など、細かいことも気になってすべて手配しました。本当はそこまでしなくて良かったのかもしれませんが、結果的に多くの作家さんたちがとても喜んでくれました。でも、体力的には限界で、これまで3度ほど救急車で運ばれました」
開催準備の拠点とするために、開墾場内の一角を借り受け、「くらふと松ヶ岡こぅでらいね」をオープン。(『こぅでらいね』は庄内弁の『こでらいね=こたえられない』をもじったもので、『堪えられないほど気持ちがいい』という意味)ここを拠点に、地域の人の協力も得ながら開催の準備が進められた。
庄内クラフトフェアin松ヶ岡は、2年目は1万人、3年目以降は2万人が来場するまでとなった。何事も全力以上、200%で向かう石堂さんのもてなしは、訪れるクラフト作家の間でも評判になった。10年の節目を迎えた2014年を最後にすると伝えると、作家たちによる異例の慰労会が開かれた。「これほど心のこもったクラフトフェアは他になかった」と感謝されたという。


「庄内クラフトフェアin松ヶ岡」は春の風物詩となり、多くのファンが訪れた
現在の活動内容
松ヶ岡開墾場は2017年に日本遺産となり、さらに多くの観光客が訪れる名所となった。現在は複数のクラフト作家の作品を展示する「こぅでらいね」の床面積も広がり、展示会も定期的に開催している。クラフト作家が指導する各種制作体験ができるのも、魅力のひとつだ。



「くらふと松ヶ岡こぅでらいね」
「今まで松ヶ岡の人たちは、クラフトフェアに協力してくれただけでなく、松ヶ岡開墾場の維持のために人知れず尽力されていることを後で知りました。私も松ヶ岡のため、地域の歴史を伝えるためになることをしたいと思い、この土地の養蚕文化を象徴した『まゆ』を使った作品づくりを始めています」と、石堂さん。
2018年には「まゆクラフトデザイン展」を初開催し、「民芸品にはない新しい形のまゆ」に挑戦中だ。目指すは〝日本一のまゆカテゴリー〟。シルクで作られたウエディングドレスに、まゆやシルクを使ったブーケを合わせるチャレンジもした。今は蚕が初めて吐く糸を使ったコサージュも作っている。
まゆは、見た目よりも硬くて扱いづらい素材。だからこそ面白さがあり、試行錯誤による経験値がものをいう世界だ。
「既存のものと同じ作品を作りたくないんです。作りながら、こうしたら面白いんじゃないか、もっとこうしたら……と考えているとワクワクします」



左がまゆで制作した雛人形、右はシルクで制作したブローチ
今後の目標・メッセージ
「これから何かをしようと思っている方がいたら、『やらないで後悔するよりは、やって後悔してください』と言いたいです。未熟なのは当然。今は簡単にネットでやり方がわかるけど、本質は実際に経験しないとわからないもの。若い皆さんには、自分が目指す世界のトップを自分の目で見ることと、その歴史を知ってもらいたいと思います。そうすれば自分の今いる位置がどこか、よく分かりますよ」
山形のクラフトブームの先駆けとなった石堂さん。これからはさらに〝『こぅでらいね』な空間、居心地のよい空間〟として愛されるように、日常を忘れて制作体験に没頭できる環境を作りたい、と話す。カラフルなまゆに囲まれて、今日も作品を作り続ける。