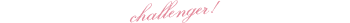プロフィール
2002年 鈴木酒造合資会社社長に就任
2015年 月山酒造株式会社代表取締役社長に就任
チャレンジのきっかけ
鈴木和香子さんは、朝日町で江戸期から続く酒蔵、鈴木酒造の次女として誕生。二人姉妹の次女だったため、自分はいずれ家を出ることになるだろうと考え、教員を目指し関東の大学に進学していた。しかしながら、姉が嫁ぐことになり突如、酒蔵の後継として白羽の矢が和香子さんへ。2001年に社長を務めていた父親が逝去したことから、和香子さんは鈴木酒造の社長に就任することになった。
「酒蔵の娘なのですが、実は私はアルコールアレルギーなんです。一滴もお酒は飲めなくて……。社長なんて無理!と言いましたけれど聞き入れてもらえず、なされるがままでしたね。」(和香子さん)
チャレンジの道のり
そもそも酒造りの世界に、女性・子どもは禁制。古くから男性の仕事だった。ただ、女性にもできる仕事はあり、和香子さんも子どもの頃から、祖母や母と一緒にラベル貼りや、米を蒸す際に使う布の洗濯など裏方の仕事を手伝っていた。
しかし、社長に就任したことで状況は一変。顧客対応を行うためには酒造りに関する知識が必須だと考え、蔵に入り酒造りを経験することになった。もちろん古くからの蔵人は戸惑い、「女が蔵に入るのか。」と当初は歓迎されなかったという。
和香子さんは蔵での酒造りに入る前から、山形県の工業技術センターで開かれていた醸造の研修会も参加していた。これまで酒の製法は蔵ごとに門外不出とされていたが、このままでは山形の酒造りがダメになる、と危機感を持った同世代の蔵人が集まり、各酒蔵のデータを持ち寄って勉強会を開いていたのだ。和香子さんは、主にお茶出しなどの手伝いをしていたのだが、一緒に勉強しようと誘われ、自然に溶け込んでいった。
「私が蔵に戻った頃は、酒造りの表舞台に女性の姿はありませんでした。例えば、問屋さんの展示会や商談会に足を運べば、会場のスタッフと間違えられたり、『あなたに日本酒のことを聞いてもわからないよね』と言われたり……。また、技術セミナーに足を運べば、他のイベント会場に案内されたりもしました。それほど、酒造りの現場に女性がいることは普通ではなかったのでしょうね。でもその悔しさがあったからこそ、奮起することができたのかもしれません。こうした中で、私をすんなりと受け入れてくれた研醸会の勉強会の仲間は、心強い存在でした。感謝ですね。」
現在の活動内容
和香子さんに影響を与えた出会いは他にもある。まずは、「るみこの酒」で全国的に名高い三重県の森喜酒造場の麹造り責任者、森喜るみ子さんだ。酒造りに携わる女性のコミュニティを作ろうと、森喜さんが全国紙で呼びかけた記事を読み、縁が繋がった。その後、森喜さんを中心に蔵女性サミットが発足し、和香子さんもスタート時からのメンバーに。現在に至るまで酒造りに関わる女性の輪を広げる活動に参加している。
「多くの女性と出会う中で、『酒造りに男女は関係ない。技術者はいいものをつくることを頑張ればいい。女を売り物にすることなく、男性以上に知識を身につけよう』という言葉がとても印象に残っています。」
農業との関わりを再認識した出会いもあった。鈴木酒造の隣、大蕨地区の棚田が、後継者難でオーナー制度を始めたという話を聞き、和香子さんもオーナーになり、栽培したはえぬきで酒づくりを行った。季節ごとに農作業を続けるうちに、酒造りをする自分たちも、自然の恵みに感謝する農家と同じ。酒づくりは農業の延長なのだとハッとしたという。
こうして一歩ずつ酒造りの世界で歩みを進めるうちに、酒蔵にも変化が起こった。鈴木酒造を含む3つの酒蔵が名を連ねて設立した、月山酒造株式会社の社長を務めることになったのだ。
「月山酒造を構成する3つの酒蔵は、いずれも親族が営んでいました。社長が代替わりすることになり、一番年上という理由だけで、私が社長になってしまいました。」
規模が大きくなった会社の社長を務めることになり、肩に力が入る和香子さんを支えたのは家族だった。
「社長とはいっても、取締役の中でハンコを管理する代表というだけ。あまり重く考えるな。と主人から助言がありました。3人の子育てなど家のことは主人がフォローしてくれ、本当にありがたかったですね。」
仕事の愚痴を言いたくなって口を開けば、ご主人が甘いお菓子を放り込んでくるのだそう。そのお菓子をもぐもぐと食べている間に、不思議と気持ちの整理がつく。日常のこうした何気ないサポートが、和香子さんを支えたのだろう。
会社のトップとはいえ、事務全般やギフトのラッピングなどなんでもこなす。杜氏が体調不良になったときには、代わりに蔵に入り、20kg近い米を担ぐこともある。
「自分主導というよりも、周囲の状況や時代の流れにおされて社長になったといっても過言ではありません。そんな私にとって、家族と仲間が支えです。元々公務員だった主人も、今は取締役として叱咤激励してくれています。毎日がいっぱいいっぱいで、匙の投げ方もわからないまま、ただ日々を積み重ねてきただけなんです。」
こう話す和香子さんだが、月山酒造の酒は2014年、2015年のインターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)で金メダルやグレートバリューアワードを受賞。着実に成長を続けている。



今後の目標・メッセージ
「私が酒造りの世界に入ったときのことを若い世代に話すと、『いつの時代?江戸?明治?』と笑われるほど、今は女性が酒造りに携わることは普通のことになりました。また、近年日本酒は『SAKE』として世界に認められる存在になってきています。若い社員たちが、『こういうラベルを取り入れたい』とデザインを提案してくるのですが、斬新なデザインで、いつも私は驚かされています。『よその蔵ではこういうラベルが主流になっている。おかあさんの頭は化石!』と冗談交じりに言われますが、日本の伝統文化の1つといっても過言ではない日本酒に対して、どこを変えて、どこを守っていくかというのは、これからの世代に伝えていかなくてはいけない大事なポイントだと思います。時代の流れに伴って、古き良き日本の文化は徐々になくなっています。これまで造り酒屋では、24節季ごとに行事を行っていました。そういった風習も今は少なくなっています。漬物って自分の家で漬けるものなの?と驚く若者もいます。私は長い歴史の中で伝えられてきた風習を残しながら、日本酒が持つ奥深さを伝えていきたいと思います。」
酒造りは農業と同じ。その農業も今は高齢化によって変革が求められている。江戸時代から続く酒蔵に生まれた和香子さんは、これからの世代を見守りながら、蔵の成長、日本酒の発展を下支えしていく。