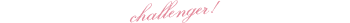プロフィール
1958年 寒河江市生まれ、山形市在住
1990年12月 出産のため退職
1995年 育児サークルに参加
1998年 「やまがた育児サークルランド」発足、2003年にNPO法人化
2010年11月~2012年10月
山形県男女共同参画審議会委員(公募)
2011年~2013年
山形県男女共同参画センター「チェリア」に勤務
2017年1月~ 山形県男女共同参画推進員
2020年6月~ 山形市市民活動支援センター所長
育児サークルへの参加をきっかけに子育て支援、男女共同参画などの社会的活動に関わる。
ほかにも
山形県ネイチャーゲーム協会理事
市民活動団体CAPやまがた事務局長
ガールスカウト山形県第6団委員長
山形市青少年健全育成推進員
山形県スポーツタレント発掘実行委員会事務局
山形県環境教育推進協議会委員
山形県環境審議会委員
JAF山形支部交通安全実行委員会委員長
など幅広い分野で活躍。
チャレンジのきっかけ
結婚して夫の両親と同居し、当時は行政関係の団体で働いていたが、出産が近くなり退職した。正職員ではなく、今のように産休や育休が当たり前という時代ではなかったこともあるが、その頃は寿退社や出産退社は普通のことで、仕事を辞めることにそれほど抵抗も感じなかった。
家庭に入り、1991年1月に男の子を出産した。息子は可愛いが、家にいて子どもの世話をしているだけの毎日に満たされないものがあった。やはり社会とのつながりが欲しかった。初めての子育てで不安もあり、近くに同じ年頃の子どもがいればママ同士でおしゃべりしたいと思い公園に行ってみたが誰もいなかった。義父母も違う土地から移り住んでいたので地域とのつながりが薄く、近所にどんな人が住んでいるのか、子どもがいるかどうかを聞いても分からなかった。
人生が大きく変わったのはその年の8月8日だった。義父母は初孫の息子をとても可愛がってくれた。その日も7カ月になった息子は義母に抱っこされ、スツールに座って体を揺らす義父を見てキャッキャと大喜びしていた。そのうち義父は勢い余ってスツールごと後ろに倒れ、頚椎を骨折して脊髄の中の神経が切れてしまい、一瞬で肩から下が動かない全身麻痺になってしまった。
この時から生活が一変した。義父が退院すると1つの部屋に介護用のベッドとベビーベッドを並べて置き、義母と交代で2人の世話をした。まだ介護保険制度もない時代で、初めての介護と初めての子育てで24時間気が抜けず、毎日夢中だった。
そうした中で2人目の妊娠が分かったが、切迫流産と切迫早産で出産までの10カ月間、入院生活を送ることになった。その間、息子は平日は保育園に預け、土日は実家の両親にみてもらい、夫と義母で2人の世話をするという綱渡りのような日々が続いた。1993年9月に娘が生まれ、家に戻るとまた子育てと介護の日々が始まった。その後、義父が亡くなり、3年半続いた介護が終わった。「精一杯やれることはやった」という思いだった。
義父の納骨が済んで一区切りがつき、ようやく自分の時間が持てるようになった頃、「育児サークルに参加してもいいか」と家族に相談した。1990年代に入って少子化と地域の人間関係の希薄化を背景に、全国で育児サークルの活動がとても盛んになっていた時期だった。介護中は外に出ることはなかなかできなかったが、以前から子育てをしているママたちと交流したいという思いがあり、市報や公民館だよりを見て情報を集めていた。夫や義母も賛成してくれ、2歳になった娘を連れて東部公民館の育児サークルに参加するようになった。1995年のことで、それが今の活動につながる原点だった。
チャレンジの道のり
2年後、娘が幼稚園に入るため育児サークルを卒業することになった時、サークルのリーダーから一緒に山形市内の育児サークルの連絡会を作らないかと声をかけられた。当時、さまざまな育児サークルが活動していたが、横のつながりがなかったため、ネットワークを作って情報交換し、共通の問題を解決しようという目的だった。
そこでリーダーと自分を含めた6人のママが発起人になり、「やまがた育児サークルランド」(代表・野口比呂美氏)を発足。理事として子育て支援に関わることになり、これが社会活動の第一歩になった。「やまがた育児サークルランド」はその後、山形市七日町に「子育てランドあ~べ」を開館し、NPO法人となり、次第に活動の場を広げていった。
この頃、男女共同参画推進のための拠点施設として山形市男女共同参画センター「ファーラ」、山形県男女共同参画センター「チェリア」が相次いで設立された。「やまがた育児サークルランド」は両センターに団体登録し、会議室を借りたり印刷機を利用したり、活動の支援を受けるようになった。
その中で初めて「男女共同参画」の考えに出会い、目から鱗が落ちるようだった。男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野に共に参画する豊かな社会をめざすという理念は、子育てする上でも一人の人間としてもとても大事なことで、社会生活の中で何かモヤモヤしたり、生きづらさを感じたのは、この男女共同参画的な視点がないためではなかったかと衝撃を受けた。
これがきっかけで男女共同参画について深く知りたいと思い、女性人材養成講座・ファーラ大学に3期生として参加。2年間の講座を修了し、ちょうどスタートした女性リーダー育成講座・チェリア塾の1期生になった。チェリア塾では1年目に男女共同参画について基本的なことを学び、2年目は塾生自身が地域で男女参画を実現していくための講座を企画し開催するなど、実践的なことを学んだ。
家族は、男女共同参画とは何かあまり理解はしていないものの、私が勉強や活動することには反対しなかった。だが当時は、女性がプライベートな時間に男女共同参画などを学ぶということは今ほど一般的ではなく、周りに気兼ねして家から出かけにくいという人もいた時代だった。
チェリア塾を修了した後も、「男女共同参画というものを自分の軸として子育ても仕事も社会活動もやっていく必要がある。自分のライフテーマはジェンダーだ」と思った。子どもの年齢が上がるにつれて、子育て支援から男女共同参画そのものの活動に参加したいという思いが強くなっていた。そこで、一緒に学び合ったチェリア塾1期生の仲間と2006年に「桜桃(チェリア)の会~やまがた女塾~」を結成し、活動を始めた。
その後、2011年から3年間、チェリアの嘱託職員として男女共同参画に関わった。1年目は事業企画、2年目は男女共同参画の相談員、3年目は総務・会計・運営一般と全てのセクションを担当させてもらい貴重な日々を送った。
嘱託契約が終わると山形市市民活動支援センターから、男女共同参画の視点を生かして市民活動の支援をやってみないかと誘われた。このセンターはNPOや市民活動団体、ボランティア団体など、市民活動・公益活動を行う団体の中間支援の活動を行なっている。男女共同参画の分野だけでなく環境や福祉などさまざまな分野の登録団体に関わることになるので、より幅広い分野で男女共同参画の視点を取り入れるアドバイスができるのではないかと考え、職員になった。
現在の活動内容
2017年から山形県男女共同参画推進員の活動をしている。男女共同参画の普及啓発のため、出前講座の講師として県内各地の市町村や地域サークルの勉強会、企業の研修会などに出向き、男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに関する講話やワークショップを行なっている。最近では、保育園の保護者の集まりで、家庭の中の家事分担のワークショップを行なった。それぞれの家庭で、食器洗いやゴミ出し、買い物など、さまざまな家事を誰がやっているか、現状を“見える化”し、グループごとに感想を話し合ってもらった。お父さんお母さん双方からいろいろな話が出て、最後に理想的な家事分担を考えてもらった。
こうした出前講座などには、以前は1人で出向いていたが、県内各地に若い世代の男女共同参画推進員も増えたので、現在はその若い仲間と一緒に講座を行うようにしている。自分が気づかない視点もあって勉強にもなり、男女共同参画推進の活動を継続して進めていくために、次の世代のアドバイス役になれればと考えている。
2020年からは山形市市民活動支援センターの所長を務め、NPOなどの中間支援のほか、さまざまな講座を企画し開催している。2030年までに達成すべき国際目標として日本でも積極的に取り組んでいるSDGs(持続可能な開発目標)の5番目が「ジェンダー平等を実現しよう」であることから、2021年にはSDGsミーティングを開催。「ジェンダーの観点から誰一人取り残さない社会を考える」をテーマに、チェリア館長の伊藤眞知子氏ら3名のパネリストを迎えてパネルディスカッションを行なった。
また、研修会などの講師に招かれることもあり、昨年は酒田市男女共同参画センター「ウィズ」の登録団体研修会・情報交換会で、「無意識をイシキする“アンコンシャス・バイアス”を知ろう」をテーマに講演した。
このように、社会が少しでも男女共同参画社会の実現に向かう力になればという思いで、さまざまな活動しているところだ。


出前講座にて

今後の目標・メッセージ
「ジェンダー」という言葉を耳にすることが多くなったが、まだまだ理解されていないと感じることが多い。そこで、身近にあるジェンダー問題について考え、理解を深めてもらいたいと、以前から一緒に活動している市民活動団体「ちぇりっぽ(女性=健康Yamagata)」の仲間と「ジェンダーカード」を考案した。チェリアの山形県男女共同参画県民企画事業に応募して採択され、作成したものだ。
このカードは、地域・職場・家庭・学校の4種類で構成し、楽しみながらゲーム感覚でさまざまな場面でのジェンダー問題を深めることができる。こうしたツールを使って、男女共同参画やジェンダーについて親しみながら学んでいく機会を提供していきたい。
また、昨年、山形県が発行した「男女共同参画の視点に配慮した表現のガイドライン─公的広報の手引き─」(全12ページ)https://www.pref.yamagata.jp/documents/32043/p01–12min.pdfの作成に関わった。このガイドラインは、行政が公的な広報をする際、さまざまな立場にある受け手の個性を尊重しながら、共感が得られるよう、男女共同参画の視点から気をつけたい内容をまとめたものだ。基本的な考え方をはじめ、よくありがちなケーススタディ、チェックリストや改善前と改善後のポイント、表現に関するQ&Aなどを分かりやすく掲載している。
行政のチラシやパンフレットなどでは、「キーマン」「父兄」「兄弟」「女性ならでは」といった言葉や、「家事は女性、仕事は男性」的なイラストなど、気になる表現をいまだに見かける。公的な広報は広く配布されるため、影響力が大きい。広報活動には、ぜひこのガイドラインを積極的に活用してもらいたい。男女共同参画の視点に配慮することは、山形県が目指す「互いを認め合い、共に助け合い、誰もが希望する生き方で輝ける社会」の実現にも通じると考えている。
今は、男女共同参画に関心がない人もいると思う。しかし、男女共同参画は人間が生きていく上でとても大事な視点の一つで、本当に男女共同参画が実現した社会は誰もが生きやすい社会になると確信している。これからもみんなで一緒に男女共同参画の活動を進めていきたい。